社会情報学科の教員は、15名。
学生定員が80名ですので、きめ細やかな少人数教育を実現しています。
それぞれ、下のような研究領域をもっています。
情報処理(2013年4月新コースとしてスタート)
データ解析とコンピュータ

森 裕一 研究室
社会における諸問題を統計学とコンピュータを駆使して、情報の観点から解析
データ解析とコンピュータ

黒田 正博 研究室
統計的手法に基づく社会調査データの連関構造の視覚化と推論に関する研究
経営・経済
経営情報学

水谷 直樹 研究室
経営学と情報学を学際的に扱う領域で、ビジネス分野の問題解決におけるコンピュータ活用を研究
経営学

山口 隆久 研究室
社会経済を理解するための基礎的な金融・経済概論を始めとして、企業経営、経営や財務戦略を研究
流通・マーケティング

大藪 亮 研究室
消費者や市場への対応に取組む企業の活動について,マーケティング論や流通システム論を研究
マクロ経済学

三原 裕子 研究室
少子化、高齢化を引き起こすメカニズムを探り、これらの現象が経済成長に及ぼす影響を考察・研究
法政・社会
マスメディア論

八木 一郎 研究室
報道のあり方と社会意識の関係を研究。表現の自由とメディア、人権と報道を考え、課題解の糸口を探る
国際政治経済学

松村 博行 研究室
日々変化する国内外の政治問題を題材に現代という時代の特徴を捉え、社会がとるべき道筋について研究
法学・情報法

川島 聡 研究室
国際人権法と障害法、特に障害者権利条約と差別禁止法を研究について研究
歴史・文化
考古学

小林 博昭 研究室
先史・古代の道具において、その製作技術や使用方法を研究。当時の人々の栽培や食用植物などの解明
アジア学・交流史

志野 敏夫 研究室
東アジアの歴史、および中国の皇帝制度を支える軍事制度を、皇帝制の成立した前後の時期において研究
博物館学・考古学

徳澤 啓一 研究室
東南アジアの土器作り、民族誌等を参照しながら、日本古代の土器作り技術を研究
記号・科学・論理

中島 聰 研究室
科学技術の文化史的背景や構造の研究。日欧米の事例研究による科学技術政策リサーチの手法を学ぶ
言語文化情報
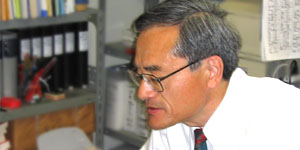
西野 雅二 研究室
19世紀ドイツ文学を研究。語学文学理解にパソコンが役立つかを検証、ドイツ語情報処理にも取り組む
英語学

河本 誠 研究室
英語と日本語の文法を比較しながら、言語を研究。語順、時制、分詞の使い方、歴史的変化等の研究
教員についての詳しい情報は、こちらをご覧ください。