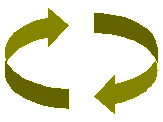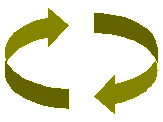「情報数学」サポートページ
1. 数学教育の変遷
1.1 数学教育の変遷
- 寺子屋時代(江戸時代)
- 明治前期
- 黒表紙(明治38年〜)
- 緑表紙(昭和10年〜)
- 生活単元学習(昭和22年〜)
- 系統学習(昭和33年〜)
- 現代化(昭和43年〜)
- ゆとり(昭和56年〜)
- 多様化(平成2年〜)
- 新指導要領(平成14年〜)
- 内容精選(約7割へ)
- 総合的学習の時間
- コンピュータと情報通信ネットワーク
- 数学選択枠の拡大
|
論理的(説得的) |
<−−−> |
直観的(体得的) |
|
| 江戸時代 ↓ |
|
|
寺子屋 |
|
| 明治前期 ↓ |
|
明治前期 |
|
|
| 明治38年 ↓ |
黒表紙 |
|
|
|
| 昭和10年 ↓ |
|
緑表紙 |
|
|
| 昭和22年 ↓ |
|
|
生活単元学習 |
|
| 昭和33年 ↓ |
|
系統学習 |
|
|
| 昭和46年 ↓ |
現代化 |
|
|
|
| 昭和56年 ↓ |
|
ゆとり |
|
|
| 平成2年 ↓ |
|
|
多様化 |
|
| 平成14年 ↓ |
|
|
|
新指導要領?? |
1.2 新指導要領と情報教育
学習指導要領
- 完全週休5日制
- 内容精選(約7割へ),数学の選択
- 総合的学習の時間
- コンピュータと情報通信ネットワーク
- 高等学校「情報科」
1.3 問題となっていること・問題となること
- 幼児教育からの問題: 前教育要領「あそび」
- 子どもの誘導が重要 = 先生の力
- 基本 = 国語と数学
- 精選を認めるなら,内容の削減の方向が時代にマッチしていない
- 例1:確率・統計の内容
- 例2:関数は,y = ax2
まででよいか?
- 「総合的な学習の時間」はよい
- ただし,生活・理科・社会・地域・ボラティア・受験勉強に偏る可能性あり
- いずれも必要だが,数理に関する観点が抜け落ちない工夫が必要
- 学力低下
- 3割削減×教師の努力目標7割 = 全体1×0.7×0.7=0.49 以前の半分!
- 教師の資質,取り組み方が問われている
- 「生徒指導に忙しいので,教科教育どころではない」は間違い!
子どもを学ばせるのが一番の仕事=教科教育
1.4 数学は何のため
- 生きるための数学
- 数学的モデリングのプロセス
| 現実モデル |
数学化
→ |
数学モデル |
| 条件整理 ↑ |
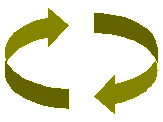 |
↓ 数学的処理 |
| 現実事象 |
← |
数学的結果 |
[次へ] [授業計画へ] [講義資料へ] [トップページへ]