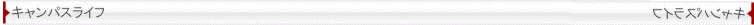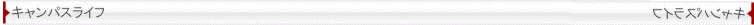|

(写真1)
|
午後12:30。牛窓港から渡船をチャーターしました。天気は残念ながら曇ぎみでした。牛窓港から黄島港まで約15分かかりました。
今回、「黄島貝塚」を巡検したのは、博物館実習を履修している社会情報学科の地域人間情報専攻の学生4名と情報社会システム専攻の学生1名、計5名です。考古学、歴史学を勉強している学生が中心です。小林博昭ゼミの小沢加枝さん・佐藤弘和くん・内藤博くん、志野敏夫ゼミの池澤恵梨さん、森裕一ゼミの太田明宏くんです。また、同行していただいたのは、自然科学研究所の白石純先生と社会情報学科・博物館学芸員課程の徳澤啓一先生です。
|
|

(写真2)
|
午後13:00。黄島に到着しました。
「黄島貝塚」は港から南西の位置にあり、丘陵上に立地しています。 |
|

(写真3)
|
黄島港から徒歩30分。「黄島貝塚」に到着しました(写真3)。史跡の案内板が立っています。黄色の○マークの部分です。
現状では、発掘調査の様子を窺うことができません。案内板のみが史跡であることを教えてくれます。
「黄島貝塚」の周辺は、何も無い原っぱになっています。見渡しても畑と海しかありません(写真4)。 |
|

(写真4)
|

(写真5)
|
|

(写真6)
|
せっかく海をわたってきたので「何か遺物はないかなぁ〜?」と周辺の探索を開始してみると、
案内板のあたりに何やら白い物が数点落ちていました(写真6)。
よく見てみると、何と貝殻です(写真7)。
もちろん海は遠くにあり、ここは丘陵地のはずのになぜ?(写真8)
それは人為的に運ばれたからであり、ここが昔は縄文人のゴミ捨て場(貝塚)だったからなのです。
再び「黄島貝塚」周辺を探してみると、あるわあるわ。数えきれないほどの貝殻が落ちていました。
|
|

(写真7)

(写真9)
|

(写真8)
|
|

(写真10)
|
「貝のほかに縄文時代の遺物はないのか!?」と活気づくと、なんと縄文土器の破片を見つけました(写真10)。
島民の方々が畑の耕作をしているため、耕されることで地中に埋もれていたものがでてきてしまったのでしょう。
結果的に貝塚跡地では、貝殻多数、土器片1点、剥片石器1点を採集することに成功しました。 |
|

(写真11)
|
午後14:00。黄島港を出港しました。
私達は船長さんにお願いして、牛窓港に戻る前に、島の裏側から「黄島貝塚」が見える場所に迂回してもらいました。
すると海上から先程私達がいた「黄島貝塚」を確認することができました。○でマークしている部分が「黄島貝塚」の案内板になります(写真11)。
|
|

(写真12) |
現在、私たちは、「黄島貝塚」で出土した土器や石器などを整理し、調査報告書を作成しています(写真12)。
よりよい報告ができるように日々全力を尽くし頑張っています!
|
| |
文:佐藤弘和
編集・写真:内藤 博 |