|
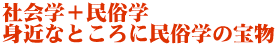
なぜ民俗学と社会学を選んだのですか?
民俗学,文化人類学それに社会学の3つを選んだといえます。これらの内,民俗学と文化人類学は,方法上の違いはあまりありませんが,対象は違います。民俗学は日本国内の習俗・習慣,信仰,伝承,芸能など,地域の文化を扱います。文化人類学は海外のあるいは自分の所属していない集団の民族文化を扱います。社会学は現代社会の構造や変化,個人と集団との関係,集団同士の関係,流行等を扱う学問です。
どれも,今生きている人達が,具体的にどのような生活をし,相互にかかわりあって,文化を伝えあるいは創造しているかということを扱うことに変わりありませんし,私が関心を抱いたのもそういったことであったわけです。
先生は体育実技でヨットを教えられていますが,ヨットの魅力は何ですか?
海が好きな人は多いと思います。海の魅力はたくさんあって,ある人は海中の生き物やさんご礁などを見るためにスキューバ・ダイビングをしますし,波が好きな人はサーフボードで波乗りをします。釣りを楽しむ人もいます。なかでもヨットは,海を楽しむ上では欲張りなスポーツです。風を上手に受けて速く走る技術,時化た海を航行する技術,船の管理や修理技術等を覚えて,遠くの海域にまで航海し,港に立ち寄れば地元の人達と交流する楽しさも味わえるようになります。風の力を利用して航海するという,世界的な伝統文化がありますから,外国に行っても,ヨットをやっているということで容易に交流できます。
海に囲まれていながら,海の楽しみ方を知らない人が多いのは残念です。ヨットという方法でなくともよいのですが,もっと海に親しんで,海の環境や景観に関心をもってほしいものです。
今後の目標はありますか?
民俗学のフィールドとして南西諸島によく行きましたが,総合情報学部が中心の「岡山学」という研究会に参加してみて,身近な所(岡山県)にわからないことがたくさんあることに気づきました。例えば,山岳信仰です。なぜ鉱物資源のある場所の近くには修験道の聖地があるのでしょうか?
それから,山間の集落などでみかける「地神」と記された石ですが,これはもともと道教の神であり,神道の神ではないので,神社の祭神となってはいないのでしょう。しかし,水神や火の神は神道に組み込まれているわけですから,地神だけを仲間はずれにするのはおかしいように思えます。こうした身近な謎も解明してみたいと思っています。
|


 高野 洋志 助教授
高野 洋志 助教授